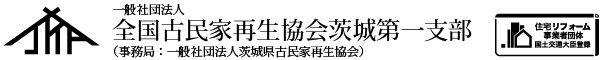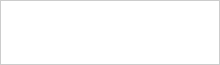おはようございます。
井上幸一氏のメルマガを引用。
住環境の視点から見た「暮らしやすさ」は現代の住環境は大きく変化しています。
都市部では高層マンションが増え、利便性は高まった一方で、近隣との関係性が希薄になりがちです。
地方では過疎化が進み、コミュニティの維持が困難になっている地域も少なくありません。
働き方の多様化により、テレワークやワーケーションなど場所を選ばない働き方が広がったことで、住む場所の選択肢も広がっています。
その結果、郊外や地方への移住を考える人も増えてきました。
一方で、住宅の高コスト化は大きな課題です。
特に都市部では住宅価格の高騰により、若い世代の住宅取得が難しくなっています。
また、高齢者にとっては、バリアフリー化やアクセシビリティの問題が重要です。
コミュニティの視点から見た「暮らしやすさ」はかつての日本社会では、地縁・血縁を基盤としたコミュニティが人々の暮らしを支えていました。
しかし現代では、そうした伝統的なつながりが弱まり、孤独や孤立が社会問題となっています。
・多世代共生型コミュニティ:子どもから高齢者まで多様な世代が交流し、支え合う場づくり
・関心共同体の形成:趣味や関心事を通じたつながりを基盤とした新しいコミュニティ
・デジタルとリアルの融合:オンラインでつながりながらも、実際の交流の場を大切にする
・助け合いのプラットフォーム:子育てや介護などの課題を地域で支え合う仕組み
など。
これからの「暮らしやすい時代」には、便利さだけを追求するのではなく、人と人とのつながりや自然との共生を大切にしながら、多様な価値観やライフスタイルを受け入れる柔軟さが求められています。
・自然との調和:緑地や公園など、自然に触れる空間の確保
・災害時や緊急時に助け合える地域の体制づくり
・持続可能性の追求:エネルギー効率の良い住宅や、長く使い続けられるデザイン
などが重要な要素になるはずです。
それでは今日も心に太陽を持って、素敵な一日をお過ごしください(^_-)-☆