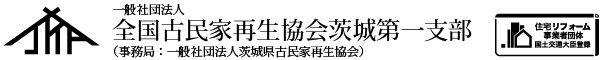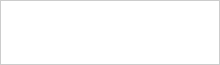おはようございます。
井上幸一氏のメルマガを引用。
判定基準の「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」
の6区分がそもそもおかしくないですか?
壊す基準でなく、残す基準なら「残せる」「危険だが残すべき」「解体すべき」位で判断した方が正しいと私は思います。
(環境省さんの立場ではしょうがないとは思いますが・・・)
残す為どうするか?そのジャッジメントを所有者が「住みたい「売りたい「貸したい」の判断材料をお伝えすると同時にその時の「費用と活用方法」も明示しなければなりません。
無料で応じる窓口を役場等7箇所に開設して、所有者のご意向に応じて、現地に赴いての修繕可能性調査と修繕方法の提示、見積がとれる修繕業者の紹介などを行いました。
窓口相談だけでなく、区長や住民を交えた意見交換も実施ししました。
そこでは「急いで知らせないと、どんどん家がなくなっていく」「残せるものは残すべき。そういう話は気持ちが明るくなる」「解体業者が解体を始めた次の日に相談窓口のチラシをみた」「活用できる可能性があったのかと残念に思った」などの意見が出されています。
環境省の災害廃棄物対策検討会で「現場の自治体と環境省との感覚にずれがある」「何もかも解体するのではなく、修繕で進めていく時期に来ているのではないか」「今後の復回復旧も考えた議論が必要だ」との意見も出されて、環境省庁も「住民に修繕の選択肢があることを早い段階でどう伝えるか、現状の把握が必要で、関係省庁ともコミュニケーションを取って検討したい」との回答をして、2月には石川県と環境省は、能登半島地震やその後の豪雨災害で全半壊した建物の公費解体加速化プランを改定しています。
活用に向けたマッチングへ古民家再生協会が中心となり県主催で12月より「被災家屋活用推進タスクフォース」会合を隔週開催、民泊施設等としての活用を考えたい事業者向けセミナーや「集落まるごと」の利活用プロジェクトを考えたい事業者向け視察ツアーなどを実施しています。
マッチングを進める中で問題になったのは「個人情報の取り扱い」でした。
調査した建物をの情報をどのような形で活用事業者に提示していくか?
古民家再生協会の運営する情報サイト「古民家住まいる」に無料掲載し、活用事業者からのお問い合わせに対して、所有者に情報をお伝えして、了解が得られればマッチングしていきました。
また、ユーチューブでの空き家の情報の配信や、古民家のリノベージョンコンテストなどでの能動的発信も計画して創造的復興に向け、所有者が住んだり、活用できなくても次の担い手が活用するなどあらゆる可能性を求めて文化/景観/環境/経済的に価値の高い古民家をできる限り未来に残すことができ始めています。
これからが本当の勝負所になります。
それでは今日も心に太陽を持って、素敵な一日をお過ごしください(^_-)-☆