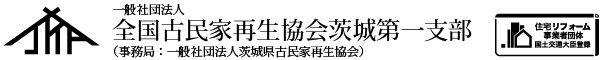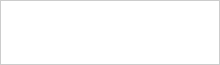おはようございます。
井上幸一氏のメルマガを引用。
ICTの向上により、パソコンをはじめとした電子機器の普及による、手書きとされる自身の手で文字を書くという行為があらゆる場面、あらゆる世代にとって少なくなってきていることです。
この「手書き」という行為について(東京大学大学院総合文化研究科)酒井邦嘉教授は「紙の手帳への手書きのほうが、紙と書き込んだ文字の位置関係など、書いた内容を思い出す際の手がかりが豊富であるため記憶の定着に有利である。」と見解を示しています。
また「使用するメディアによって記銘に要する時間が異なり、想起時の成績や脳活動に差がある」事にも着目した上で、手書きなどの行為に対して「自分の考えをまとめ、それを批判的に見直すだけの時間的な余裕があることを指摘するとともに、脳は内容を吟味し、理解し直し、表現を改めて創造的に出力するという検証を繰り返している」
と述べています。
SNSなどは、脳にとって不自然な入出力となり、本来の解釈や表現という大事な過程がおろそかになってしまうと同時に、上手く伝わらないことがきっかけとなり「決めつけ」の応酬につながるリスクも高くなってしまうというのです。
さらに酒井邦嘉教授は、AIの進化で総合的に物事を考えて判断する機会が少なくなることで結果、人の意見を聞いて譲歩したり、折り合いをつけたりするということが不得意になり「自己主張や他者への批判ばかりが強くなってくることで社会の分断にもつながっている」
と考えています。
こうした傾向はすでにSNSにおいて、大勢の人がフェイクニュースに流されてしまったり「言ったもの勝ち」のような投稿が散見されたりといった形で既に顕在化しているという現状があります。
デジタル化によって、社会に対して生産性の向上や効率化などの大きな恩恵をもたらしてくれています。
しかしながらこの方向性によって損なわれる負の側面もあるようです。
それでは今日も心に太陽を持って、素敵な一日をお過ごしください(^_-)-☆